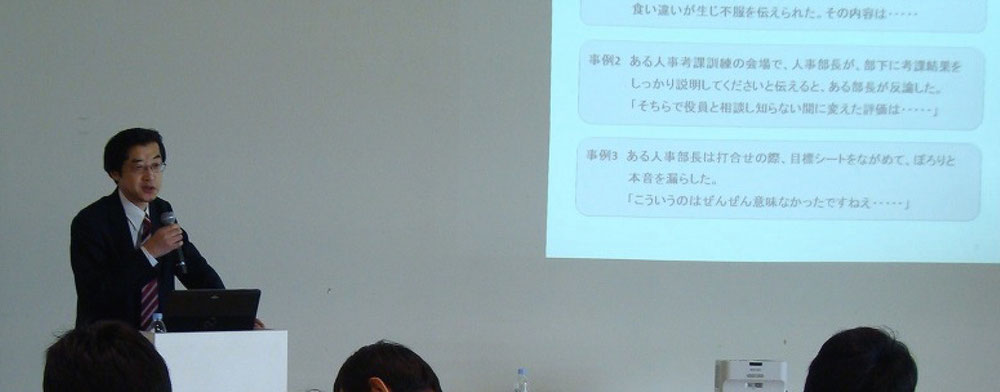■深謝
独立してマネジメントフロンティアを設立してから、あっという間に14年目になった。ここまでご支援をいただいた、クライアント並びに、アソシエイツとも言うべき関係者の方々に、改めて深く感謝申し上げたい。
特にこの何年間かは、現場の仕事が繁忙で、ホームページに記事を載せるいとまがほとんどなかった。もともと私は現場が大好きで、間接的な活動に時間を費やすことをあまり望まなかったので、私にとっては好適だった。だが、ぼつぼつ、いくらなんでもと思い、また関係者にも言われて、ここで筆を執っている。ともあれ、余計なことを考えずに仕事に打ち込んで来られたと言うことは、誠にありがたく、幸せなことであった。
現場が好きだということは、特定のクライアント企業の、特定の人物達の、特定の出来事、問題、その特定の解決プロセス、そしてその特定の方々の変化と成長に深い関心があるということでもある。この仕事にあっては、関わった人が成長したあかしを目にするほどの喜びはない。
と言って、著書にもホームページにも、そういう特定の内容をじかに書くわけにはいかない。一般化、抽象化した表現を取らざるを得ない。やはりありがたいことに、そのような表現に対しても、一定のご支持を頂けることができたので、長い歳月を、コンサルタントとして歩むことができた。関係の皆様に、再度にわたり深く感謝申し上げたい。
この間、たった10年あまりの間でも、世の中が随分変化したことにより、人材マネジメントや人材教育の分野も大きく変わったものだと思う。
■振り返り面接
現在の私が、一番時間を割いているのは、面接である。振り返り面接、動機づけ面接とでも称すべき面接となる。対象となるのは、もちろんクライアント企業の役員、管理職、専門職、中堅社員等である。今さらカタカナのネーミングをするのもどうかと思い、振り返り面接などと呼んでいる。
ある程度定例的に行うと言う側面では、コーチングに近い。が、上述各種「特定」のことにだいぶ踏み込んでいるという意味ではかなり違うのだろう。質問をして、相手の人に深く省察して考えてもらい、問題を解決する勇気を醸成することを支援するのは、もちろん最も基本的に重要なコンサルタントのスキルではある。が、その人が迷い悩んでいることに対して、仮説であってもこのように考えてはどうだろうかと踏み込んで勇気づけることが、必要ある時にはできなければ、コンサルティングとしては不十分である。
また、私のひとつの領域である、コンピテンシー面接とも、少し趣が異なる。アセスメント的な目的はあまりないということだ。この場合の私にとっての主眼は、評価ではなく、相手の人たちが成長することにある。もちろん成長のための支援をするためには、相手の人が、今どの位置にいるかという正確な「測定」という意味での評価は必要となる。それは人事的な処遇につながる評価を意味しない。
なぜそのように推移してきたかは、またの機会にゆっくり述べたい。ここでは、そうした面接をどのように行っているか、さわりだけを述べたい。
一番大切なことは、面接対象者が、そうした面接を通じて自分の言動を、普段はできない深いレベルで振り返ることができたかということである。この点が、繰り返すが、コンサルタントに求められる最も基本的スキルである。
そうした振り返りは、つまりは学びということであり、その人の啓発や成長にとって、必須のことである。教育とは、つまりは振り返りをもたらすことである。それも定期的継続的に。普段は実務とノルマに追われてなかなかそれができない。よって、何らかの仕組み、仕掛けの中で、自分の言動を鏡に映すように振り返ることが必要となる。ここで言う振り返り面接は、そのもっとも強力なツールだと思っている。
本当に抜きん出て力量優れた人は(知的に優秀な人と言う意味ではない)、普段から深い自問自答をして、そういうことを自己完結的にできてしまう。が、一般的に言って、そんな人は百人に1人もいない。
面接後に、「今日は、普段忙しくて、よく考えていなかったこと、見落としていたことを振り返るとても良い機会になりました。次の面接の日程はいつですか。」などと相手に聞かれれば、そういう効果が強く作用していることがわかる。あるいは、こうした面接の結果を、守秘義務と不問責の原則のもとに、人事担当役員や経営者などに報告した後に「ぜひこうした深い振り返りをもたらす面接を、ほかの社員にも続けていっていただきたい」などと言われると、コンサルタント冥利に尽きるというものでもある。
■心理的安全性
そのコンサルタント側の基本的スキルは、ある側面を今風の言葉で言えば、心理的安全性を感じさせるということだろう。心理的安全性とは、空気のようなものであってはならず、面接対象者を保護するしっかりとした防具でなければならない。面接をする側に、この人には何を話しても「だいじょうぶだ」と感じさせるキャリアや感受性が伴っているということだ。この場は安全ですと、口先で言うだけでは不十分で、それを保障できる力があると思われなければならない。
その上で、よく言われるように、適切な質問のスキルが重要になる。しかし、そうした人間力なり人生経験を感じさせない相手から、何かのハウツー本から切り取ってきたような質問をされても、誰しも本心から答える気にはならないだろう。その上に構築すべき、質問の具体的技術については、以前の拙著にもずいぶん述べたし、この短い原稿にて書き尽くすことはできない。またの機会に改めて述べたい。
ごく最近発見された概念のように、あるいは流行のように、心理的安全性ということが論じられている。けれども、その種の考えは、私がコンサルタントになった頃から、優秀な先輩達はしっかりとそういう技量を持っていた。私の守備範囲の一つであるアクションラーニングの創始者のレグ・レバンスは、マネージャーたちを啓発する討議の場は、絶対に安全が保障された場でなければならないと言っている。レバンスがそのように述べたのは、もう何十年も前である。原理がシンプルであることと、それが容易に実行できるかには、天地の差があると、かのコーチングの神様ゴールドスミスも述べている。これもその例だろう。私達は、マネジメントの進歩とは関係のないはやりすたりに右往左往せず、本質を執拗に追求し続ける必要がある。自分を磨き、かつ、部下と社員の成長を望むのならば。
■面接道
「だいじょうぶだ」と思われるという意味は、突き詰めて言えば、今、話していることが、さまざまなところに伝わっていって、あとあと変なことにならないという意味だ。あとで、上司その他からおとがめを受けるかもしれないと言うのに、わざわざホンネを述べる人はいない。正直言って、ここでしっかりとクライアント側に影響力を行使できないコンサルタントが少なくない。
そういう影響力が持てないと、何でも守秘義務だと言って、面接対象者との対話内容を、厳重に鍵をかけて閉じ込めておくべきだと主張することになる。それでも、幾分かの効用はあるのだろうが、随分もったいない話である。そういう形式的な守秘義務だけを強調しても、目的に照らして不十分である。そういう場で交わされた対話は、何らかの形で、その本人の啓発と成長はもとより、組織の活性化に通じていったほうが一層望ましい。適切に活用すれば大いに効用と成果がもたらされる。守秘義務というのは、面接内容を悪しき目的に用いてはならないという意味であって、面接で話し合ったことを良き方向に活用してはいけないという意味ではない。そこを誤解している人が多い。
もちろんそうした活用には、さまざまな配慮や注意深さが必要である。その詳細の方法を、今ここで述べ尽くすことはできない。が、ひとつだけ言うと、私はクライアント関係者に対して、「不問責」ということを徹底的にお願いしている。文字通り責任を問わないということだ。ある人が何をどのように感じたかと言う事実は尊重されねばならず、そのこと自体を責めても何の意味もない。そういうことを各クライアントの中で、相当にしつこく、コンサルタントとして経営者、役員などに申し上げている。
ある人が感じたことを、すぐに正しいとか間違っているとか、意識レベルが高い低いと、評価したがる人もいる(存外に実務的に優秀な人に多いから厄介でもある)。それに対してもう一度言う。正しいか誤っているかを評価することよりも、その人がなぜそのように感じたのかを振り返って考えることの方がはるかに重要であり、はるかに値打ちのあることだと。
単に質問のスキルではなく、面接者自身の人間的側面や、クライアントに対する影響力を含んだ面接技術を、最近私は、関係者と一緒に「面接道」などと呼んでいる。もうしばらく、その面接道を極める修業を積んでゆきたい。