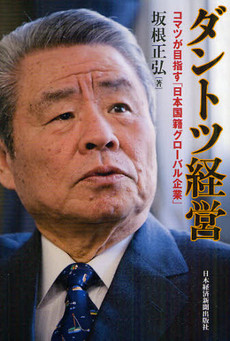
いま製造業でもっとも光っている会社のひとつが、この建設機械の大手コマツではないだろうか。そのコマツを実質10年以上率いたのが、著者坂根会長である。
本書は、コマツの改革ストーリーであり、かつ、グローバル経営の実戦論にもなっている。読む者をして飽きさせない新鮮なマネジメントの事例が次々に現れる。
コマツも、著者が社長を引き継いだ時には、たとえば自動車の日産のように大変な経営危機に直面しており、その克服には大変な辛苦が伴った。著者は、オーナー経営者ではないし、日産のカルロス・ゴーン氏のように危機に当たって外部招請された雇われ経営者でもない。会社はえぬきの経営者のおひとりである。そう言う背景の経営者にありがちな過去のしがらみに囚われず、改革にあたり強いリーダーシップを発揮できた、むしろ私たちが多くを学びうる例である。
■自分の代にどれだけ強くできるか
読み進めてゆくうちに、坂根会長が、どれほど深く自社を愛し、用語を用いればそのアソシエイツ(社員だけでなく協力企業を含め)をいつくしんでいるかがよく伝わってきた。はえぬきならではのことなのだろう。
コマツもリストラはやむなく行った。が、「やむなくリストラは行うが必ず1回限りにする」と当初から宣言していた。こう言う発言には勇気が要ることだろう。もし言葉をたがえればたちまち経営責任を問われるからだ。本書にも指摘されているように、リストラを小出しにだらだら続けたら、組織は、救いようにない沈滞に陥ってしまうだろう。そう言う会社を目にするのは悲しいことだ。
リストラをやるにしても、ただばくぜんと経費を減らせと言ってもせいぜい一時しのぎの効果しか出ないか、かえって競争力を弱める。たいていの会社は、本業と関係ない雇用に手を着けず、本業のところの変動費に斬り込み、現場や外部にばかりしわ寄せをして負担を強いる。そして景気がよくなるとまた本業に関係のない雇用を増やすから総原価の高い構造が結局変わらない。だから再度の危機を招いた時の犠牲が一層大きくなるのだと言う。
著者が、なぜ自社の収益性が低いかと分析して行くと、建設機械等の直接原価においては、アメリカのライバル企業に負けているわけではない。結局、景気の良い時に増やした本社機構や本業と関係ない子会社が、収益を圧迫するいちばんの原因となっていた。従って、大変残念だが、そちらに手を着けることになった。こうした徹底ぶりが体質強化に大きく役立った。
今は中国大使となられた丹羽宇一郎氏が、伊藤忠の社長時代、4千億円あまりの特別損失の計上と並行して、膨大な数のやはり不採算子会社をクローズした時に、一切例外を認めなかった。改革を成し遂げた経営者には、この種の不退転の決意と一貫性は、まず不可欠のようである。そう言えば、この丹羽氏もはえぬきであり、パナソニックの中村邦夫会長と並び、僣越ながらはえぬきによる経営危機改革の三傑とも称し得ようか。
先のリーマンショックの時には、協力会社組織「みどり会」においても相当資金繰りその他で行き詰まる企業もあった。こうした中で、コマツは、協力企業の在庫や機械を買い取ったり、地元金融機関に融資の口利きをしたり、口先でない本当の支援をしている。これは、間違いなく坂根会長の意思だろう。口に協力企業との共存共栄を唱えることは誰でもできる。しかしいざと言う時、こうした行動が取れる人がどれだけいるだろうか。従前からのこうした姿勢が、チャンス到来に際しては協力会社の積極的姿勢を引き出す。コマツの要請なら少々リスクがあっても設備投資しようと、コマツとぴたりと呼吸が合うのである。こうしたことが相互の高業績にどれだけ貢献するかは私たちにもよくわかる。
他方、モデルチェンジの時などは、前モデルの納入企業に一切優先権を与えずに競争させている。危機管理と健全な競争とをめりはりを着けて両立させている見事な経営手腕と言うほかはない。
本書の冒頭と末尾に2度書いておられる。「自分の代に、どれだけコマツを強くできるか」が自分の使命であると。これほど見事な、そして奇をてらわず腹のすわった経営者のミッションの表現があろうかと思う。歴史観が必要なのは、政治家だけでなく経営者も同じなのだと思う。会社はずっと続いてゆくのだ。
■貫徹した姿勢
その実行における貫徹した姿勢が引き続き随所に現れる。
コマツの強みとして有名なコムトラックスと言うシステムがある。売った建設機械が、どこで動いているのか、衛星を通じてわかると言うものだ。まず債権管理にとても有効である。代金を払わない顧客の機械はエンジンを止めてしまうこともできるのだ。しかしそれより何より、市場動向を読むのに大変役に立っていると言う。どこでどれだけ機械が稼働していることが全地球上で把握できるのだ。市場動向を他社より先読みできるし、顧客にもいろいろ有益な情報を助言できる。これはたいへん有利だ。
このシステムが、最初はオプションで15万円ほどかかっていた。よって導入がなかなか進まない。ここで思い切って坂根会長は、標準装備にしてしまった。もちろん売値を15万上げたわけではない。そのコストはコマツがかぶったのである。商品1台あたり利益が15万円減ると言うのは、商売を少しでもやったことにある人ならすぐ共感できる大変な痛みである。しかし、この決断も市場における上記のような優位性の一層の構築によりコストアップを吸収しておつりが出たようである。
一般に市場で優位な地位を占めるのは特色のはっきりした製品である。あらゆるスペック(コスト、パワー、騒音、燃費、操作性等々)において平均点以上を目指そうとすれば、特色ある製品は生まれない。開発部門がパワーを上げようとするとコストが上がり、それでは売れないと営業部門から言われる、と言った例である。たいていの会社はこの平均点主義からなかなか逃れられない。各部門の利害が葛藤し、痛み分けの調整をせざるを得ないからである。結局、かどのないまるまった月並みな商品ができて売れ行きも平凡と言うことになりかねない。坂根会長はここに大なたを振るった。従来品よりコストを10%以上節約して、それを用いて特定の重要機能において何年も追いつけないくらい他社をはるかに凌駕する商品を開発せよ、と。名づけて「ダントツ商品」である。これが書名にもつながった。
これに認定されれば経営資源が優先配分される。この承認を、社長の専権事項とした(当時坂根氏は社長だった)。こういうあたりは、いかにも改革者らしい権力の集中を図っている。この結果、開発陣が強く動機づけられ、ヒット商品が生まれ出し、コマツの高業績の直接の因となった。それまで平均点主義の商品開発を強いられていた開発技術者たちが、急にやる気を出したのは驚くばかりであったと述べられている。経営者冥利に尽きる瞬間だったろう。
■エッジと自制
経営者が貫徹する行動を取ることは、英語表現だとエッジが効いていると言うことだ。エッジの効く人は、とかく権力的になりがちな面もありうる。坂根会長にあっては、パワーの行使の際の自制のバランスがよく効いている。
経営の執行面においては、わざわざ自らの行動に統制をかけるしくみを設定し、会長、社長と言えども、重要事項を独断で図れないようにしてある。これもなかなかできることではない。自分の権力を自分で制限できる人などめったにいないものだ。ある買収案件では、役員会に条件付けをされてもたもたしているうちに案件を流してしまい、今でも買っておけば業績はもっと上がったろうと悔しがっておられる。悔しがりながら、さばさばしているのである。
重要な買収と言うような機密に属する事項は、ごく少数の関与者以外にはあまり開示しないで、最高実力者が「話をここまで進めた、さあこれでいいな、諸君」とある日通告、事実上の決定、と言うほうがふつうなのかもしれない。また一般に、やり手経営者と言うのは、経営をより迅速にするためには、一層社長に権限を集中しようと思うのが常かもしれない(実際、ベンチャー企業や、規模がさほど大きくない企業で、あまりスローモーなことをやっていたら、すぐに会社が傾いてしまうだろう。そうした企業は、力量ある人が良い意味で迅速に独裁しなければうまくゆかないだろう)。しかし、そうした独断とそれを維持するための秘密主義が、結局長い目で見れば会社を毒してしまうと言うのが著者のお考えのようだ。
こうした面からの取締役会の活性化を「コマツウエイ」の「マネジメント編」に載せて、健全な経営の継承に腐心している。オリンパスや大王製紙の件が世を騒がせているだけに、この経営姿勢の清明さは一層きわだつ。
思うに企業組織を百年健全に発展させたいと思うなら、この坂根会長のお考えはまことに至当なものだろう。しかし、幾代も後までのことを考えて経営に任じるのはよほどの忍耐、自制心が要るに違いない。自分の代でこれだけやったのだと示したくない経営者などいないだろう。
かつてドラッガーは、「ポスト資本主義社会」の中で、経営者にカリスマ性を求めるのは全く誤りであり(リー・アイアコッカやジャック・ウェルチを念頭に置いてのことだろう)、私たちに必要なのは、地道に任務に取り組み使命を果たすCEOだと言う旨を述べていた。このドラッガーのCEO像に、坂根会長はぴったりあてはまるように思えてならない。





